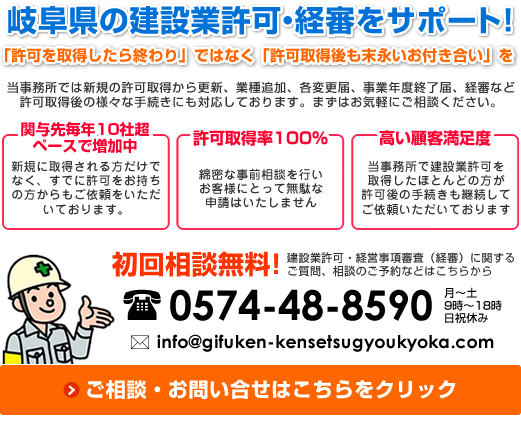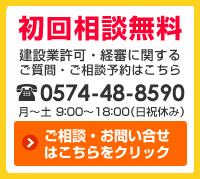建設業許可とは、500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合、1,500万円以上の工事、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)を受注する場合に必要となる許可です。
建設業許可は29業種に分かれており、2つの「一式工事」(土木一式工事、建築一式工事)と27の「専門工事」に分かれております。一式工事は、複数の「専門工事」を組み合わせ総合的な企画、指導などを行い建設をする業種になります。
「一式工事」は総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事であり、大規模又は施工が複雑な工事を原則として元請業者の立場で総合的に管理する事業者向けの業種となります。このように「一式工事」は工事全体を管理するような業種であるため、「一式工事」の許可を持っていれば、どの業種の工事をしても良いわけではなく、一式工事の許可を持っている業者が、専門工事に該当する工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要になります。
建設業許可を取得するための要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たしていることが必要です。
- 適切な経営能力を有すること
- 適切な社会保険等に加入していること
- 専任技術者がいること
- 誠実性
- 財産的基礎要件
適切な経営能力を有することについて
適切な経営能力の有することについては、以下の2つのうち、いずれかに該当していることが必要になります。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、もしくは常勤役員等及び 当該常勤役員等を直接に補佐する者 については、こちらのページで詳しくご説明をしております。
適切な社会保険等に加入していること
健康保険、厚生年金、雇用保険について、それぞれ適切に加入している必要があります。
健康保険、厚生年金の適用事業所
法人事業所及び個人経営で常時5名以上の労働者を使用する事業所が適用対象となります。なお、健康保険については、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)への加入でも問題ありません。
雇用保険の適用事業所
法人事業所、個人経営に関係なく労働者を1人でも雇用する事業所は適用対象となります。なお、労働者を雇用していない場合(法人であっても役員のみしかいない、個人経営で事業主本人しかいない 等)は雇用保険への加入義務が発生しません。
専任技術者について
許可を受けようとする業種に関して、許可を受けようとする業種に関する一定の資格、または10年以上の実務経験を有するものを営業所に配置することが必要となります。業種と一定の資格の関連性については、業種ごとの詳細解説ページをご確認ください。
専任技術者は営業所ごとに配置が必要となるため、本店と支店がある場合、両方に専任技術者の要件を満たす人を配置する必要があります。(異なる営業所での兼任は認められておりません。)
誠実性について
法人である場合、法人又はその役員等もしくは一定の使用人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
個人である場合、本人もしくは 一定の使用人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
財産的基礎について
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。
財産的基礎については、建設業許可の種類が「一般許可」「特定許可」によって要件が異なっております。財産的基礎についての詳細はこちらのページをご覧ください。